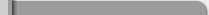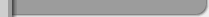時代の流れを感じながらニュースを伝える
|
ランキングバトル入賞「59分間でパソコン超ど素人主婦が情報起業できる方法」
株式投資ゴールデンルール - 超初心者のキャバ嬢でも株で1億円儲けた方法 “競馬素人”でも1ヶ月目にお札が立った!泣く子も黙るあのプロ馬券師が、遂に暴露した“楽勝”続きの100万鷲づかみ“秘伝ノウハウ”【神風競馬2】 × [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
|
ランキングバトル入賞「59分間でパソコン超ど素人主婦が情報起業できる方法」
株式投資ゴールデンルール - 超初心者のキャバ嬢でも株で1億円儲けた方法 “競馬素人”でも1ヶ月目にお札が立った!泣く子も黙るあのプロ馬券師が、遂に暴露した“楽勝”続きの100万鷲づかみ“秘伝ノウハウ”【神風競馬2】 酵母エキスの働きで肌に酸素の“ちから”を届け、はりのある肌に導く「ミッションY」シリーズの新アイテム。筋肉のこり、こわばりをほぐして血流をアップさせ、老廃物の排出をスムーズにするマッサージの効果をサポート。独自成分の「エナジーTRF」を配合。価格は5800円。販売中。 税制改正の主導権を握ってきた自民党税制調査会が苦悩している。抜本改革の議論を前に、参院選惨敗によって参院で与野党が逆転し、焦点となる消費税率の引き上げの早期実現が困難となり、今後の改正論議の方向性がつかみきれない。人材面でも手詰まり感が否めず、存在感が一層低下する可能性もありそうだ。 自民党は7日、政務調査会の調査会長人事のリストを発表した。「外交・山崎拓」「道路・山本有二」など閣僚経験のある有力議員の名がずらりと並んだが、「税制」の欄は空白。人選が手間取っているのは明らかで、政調幹部の一人は「税調は官邸を含めて上のレベルで調整しないといけない」と言葉を濁す。 来年度税制改正の最大の焦点が消費税率上げの扱いであることは論をまたない。小泉政権時代は封印し続け、安倍晋三首相も「今秋から本格論議」と先延ばししてきた。一方で09年度までに基礎年金の国庫負担割合を引き上げる財源として有力視されており、引き上げ決定に残された時間は少ない。自民税調では12月中旬に決める08年度の与党税制改正大綱に上げ幅や実施時期を盛り込むことも念頭に置いて議論を進める見通しだった。 ところが参院の与野党逆転で税率据え置きを主張する民主党の発言力が増し、税率上げを盛り込んだ法案を来年の通常国会に提出しても賛成が得られる可能性は低くなった。強引に成立させようとすれば国会の混乱を招き、次期衆院選への影響は計り知れない。 そんな中、政府・自民党内の税制改正路線は三つに分類されつつある。まず、野党に税制の論議を呼び掛けて消費税率上げや所得税、法人税などの抜本改革の道筋をつける努力をする「与野党協議派」で、現会長の津島雄二氏らが主張する。 さらに同派よりも具体的な増税論議に踏み込むべきだとする与謝野馨官房長官ら「財政再建派」、この際、消費税率上げを再び封印して経済成長を優先すべきだという「成長派」だ。税調会長の路線が色濃く反映するだけに、人選はなかなか定まらないようだ。 もっとも、税調の人材難も深刻。税調の議論をリードする「インナー」と呼ばれる非公式幹部会合のメンバー級の議員がめっきり減っている。昨年のメンバーは津島、与謝野、町村信孝、片山虎之助の4氏。与謝野、町村両氏は入閣し、片山氏は参院選で落選。党に残っている経験者は津島氏と柳沢伯夫氏だけだ。かつては税のプロとして若手を育成しながら「税の配分」という権益を守ってきた自民税調。今やその面影はなく、内外に大きな不安を抱えながら、今秋からの議論に突入する。この日の判決は、「警察の捜査全体に対する信頼を大きく損なった」と述べた。こんな調べが常態化していると見られては多くの捜査員には心外だろうが、自白を得られないあせりや能力不足が、誤った方向にいきかねない。2008年03月27日13時24分政治部 大石格(6月14日) 「会議の中身は外に出さない、ということになっている。その方が忌憚(きたん)のない話し合いが出来る」 11月13日、福田内閣初の政務官会議後の記者会見で戸井田徹内閣府政務官はこう語った。思わせぶりな言い方だが、出席者の1人は「表に出せるようなまとまった議論や中身のある話し合いをしていない」と声を潜める。基本的に26人の政務官全員が出席するため「あれもこれもと、ばらばらな注文が多く、話が前に進まない」というのだ。 副大臣・政務官制度は2001年1月の中央省庁再編に関連して発足した。英国の制度をモデルに「官僚主導から政治主導への移行」を実現するのが大義名分。法的根拠があいまいで仕事の内容がはっきりせず「盲腸」とやゆされていた政務次官制度を衣替えした。鳴り物入りの制度導入から7年近くがたつが、実効をあげているとはいいがたい。 国会審議活性化法第9条に規定がある副大臣会議は、01年1月の閣議申し合わせに基づき、官房長官と官房副長官が協議して議題を決める。副大臣会議では02年7月の「観光振興に関する副大臣会議報告」という提言をまとめ、翌年からの政府の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」につながった成果がある。 問題は政務官会議だ。政務官同士の申し合わせによって、首相官邸で月に1、2度、開くが、副大臣会議に比べて法的根拠はあいまいだ。13日の会議では「今後、政務官会議を開くかどうか」が主要議題の一つとなる始末。実績と言えば、小泉内閣時代に安倍晋三官房長官(当時)の肝いりでまとめた「家族・地域の絆再生」ぐらいだ。 副大臣は閣僚を直接に補佐するラインのポスト、政務官はアイデアを出すスタッフだ。「政務官は官僚との最初の接点。勉強になるし、官僚とも仲良くなれるということが重要なんだ」。ある閣僚こう割り切る。しかし「政策及び企画に参画し、政務を処理する」という政務官の本来の設置目的から考えると、少しさみしい感じがする。省全体への権限があるわけではなく、閣僚との連携がなければ政策決定のラインからも外れる。そのため政務官会議でも「どれくらい深く政策にタッチしているか不透明で、各省を横断する議論がしにくい」という結果になる。 副大臣・政務官制度の発足の目的の1つには、閣僚が不在の際の国会答弁の代理があった。答弁の回数は徐々に増えつつあるが、野党は失言を狙って国会では閣僚を指名する。与党内には「答弁は全部副大臣・政務官でも良いはずだ」という指摘もある。 官僚側からは「政務官に話をすれば、党の関係者に伝わるようにしてほしい」という要望も出ている。今のままでは「盲腸」から脱却したとはいいがたい。安倍内閣の発足当初は、得意分野を記入した自己申告書も参考に副大臣・政務官人事を決める方針を打ち出し、政策決定でより重要な役割を担う方向に踏み出したかに見えた。政策面で主導権を発揮してきた自民党政調会の各部門との関係も課題となり、人事の一体化まで取りざたされた。 しかし、閣僚の一本釣り人事が定着するなかで、副大臣・政務官ぐらいは、派閥均衡で割り振らないと、不満が爆発しかねなかったのも事実。結局、旧態依然とした人事決定の方式が継承された。「副大臣や政務官のポストは年齢が上の議員に譲るべきだ」。ある若手議員はこう忠告を受けたという。制度を活性化するには、もう一度原点に返って、派閥均衡でのポスト割り振りを廃し、能力重視に切り替えることから始めてはどうだろうか。 PR |
 |
 |
 |
|
|

|
|
トラックバックURL
|
|
忍者ブログ [PR] |